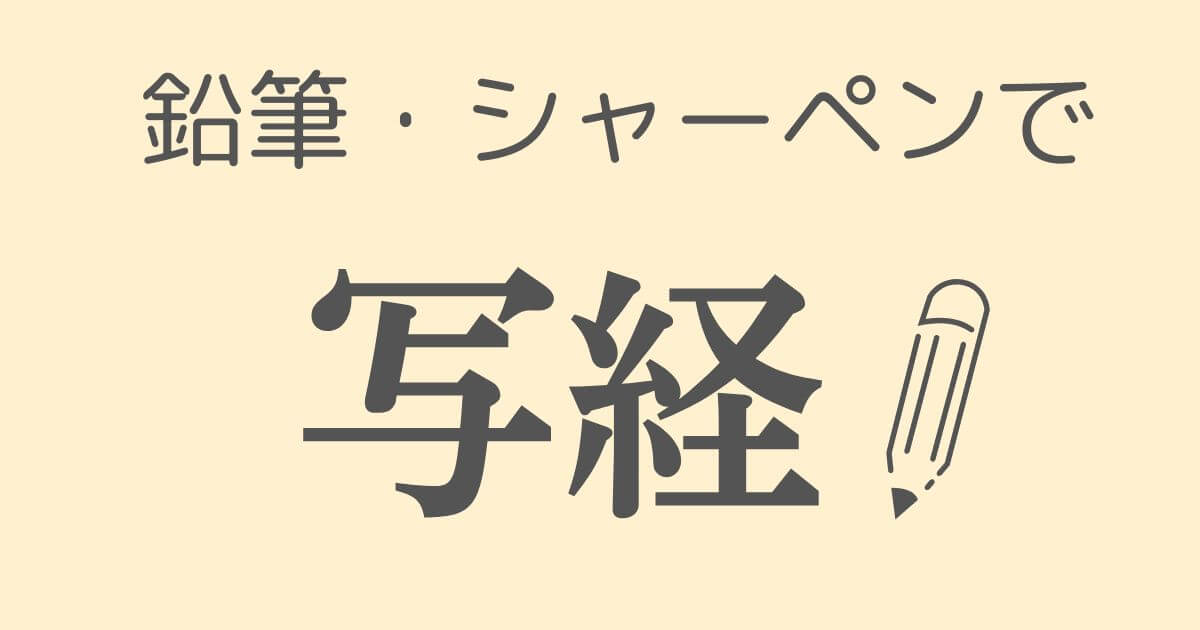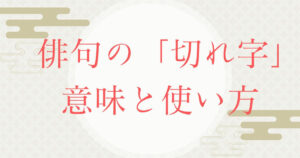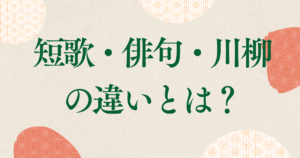写経というと、筆と墨で厳かに行うものというイメージがあるかもしれません。しかし、私はシャーペンで気軽に般若心経の写経を始めてみました。
字が汚くても、意味がわからなくても大丈夫。まずは一文字ずつ、自分のペースで。 実際にやってみると、「あれ、この字ってこう書くんだ」「意外と集中できる」など、小さな発見と気づきがたくさんありました。
本記事では、私の実体験をもとに、シャーペンや鉛筆での写経の始め方や感じたこと、続けるコツなどを紹介します。
写経を始めてみたいけど、筆はハードルが高い…」という方の参考になれば幸いです。
写経をシャーペンや鉛筆で気軽に始める
筆に慣れていないから、まずはシャーペンから
写経といえば、墨と筆で静かに文字を書く…というイメージがあるかもしれません。確かにそれが本来の形なのだと思います。ですが、私は筆をほとんど使ったことがなく、字を書くこと自体もあまり得意ではありませんでした。
それでも、「写経」というものに少しずつ興味を持ちはじめたとき、気持ちのハードルをできるだけ下げるために、まずは手慣れたシャーペンで始めることにしました。筆に比べれば雰囲気は薄いかもしれませんが、「まずは続けること」「始めること」を優先しました。
「般若心経」を選んだ理由|262文字のコンパクトさが魅力
写経に選んだのは、仏教の中でも最も有名な経典のひとつ「般若心経(はんにゃしんぎょう)」です。理由はシンプルで、262文字という分量の手ごろさに惹かれたからです。
いきなり長いお経を書き写すのはハードルが高いですが、般若心経なら1ページに収まるくらいの長さ。しかも意味が深く、調べれば調べるほど「なるほど」と思える部分も多い。写経を通じて言葉の意味にも少しずつ触れていけるのが、このお経の魅力だと思います。
部屋を整える前に、「まず書きたい」気持ち
本格的に写経をするなら、机を整え、姿勢を正し、道具を揃えて…といった“儀式”のような準備も大切なのかもしれません。でも、私の場合、それらの準備がハードルになってしまって、なかなか行動に移せませんでした。
むしろ「そんなことより、まずは一文字でも書いてみよう」と思い、書きなれたシャーペンとコピー用紙を手に取って、机の上に広げました。部屋が多少散らかっていても、正座でなくても、背筋がピンと伸びていなくてもいい。“今の自分”のままで始められる写経が、今の私にはちょうどよかったのです。
写経にシャーペン・鉛筆を使っても大丈夫?
本来の写経では筆や墨を使うのが一般的
写経という言葉から多くの人が思い浮かべるのは、「筆で墨をすり、静かな場所でお経を書き写す」という、厳かな風景だと思います。墨をする時間もまた“無心”になるための準備とされており、すべての行為が修行の一部とみなされているわけです。
しかし最近は“気軽に始める”ために鉛筆・シャーペン派も増加
とはいえ、最近は時代の変化もあり、「まずは気軽に」「日常生活の中でできる範囲で」というスタイルの写経も広まっています。お寺によっては鉛筆やボールペンでの写経を認めているところもあり、道具の自由度も高まっているのが現状です。写経は“心の修行”という意味では本来の形式も大切ですが、最初の一歩を踏み出すには、むしろ身近な道具の方が合っているという考え方も十分ありだと思います。
大切なのは「道具」よりも「集中できること」
結局のところ、写経の本質は「何を使って書いたか」ではなく、「集中できること」だと思います。雑念がすべて消えるわけではありませんが、普段の生活とは違う“心の静けさ”が確かにそこにあるのです。
道具はあくまで手段です。「筆じゃなきゃダメ」「墨じゃなきゃ意味がない」と思っていたら、いつまでも始められません。だから私は、自分にとって続けやすい方法で写経を始めたことに、むしろ意味があると感じています。
実際にシャーペンで写経してみて感じたこと
最初は字の間違いに気づき、自分の思い込みを知る
シャーペンでの写経を始めてみて、私が最初に感じたのは「あれ、この字、思っていたのと違うな」という驚きでした。自分では正しく覚えているつもりだった漢字が、実は微妙に違っていたり、書き順があいまいだったり。そうした間違いに気づくことで、「意外と自分は思い込みで日常を送っているのかも」と実感しました。
字の汚さについては、あまり気にしていません。もちろん、いずれはきれいな字で書けるようになりたいという思いはありますが、今の目標はそこではありません。まずは「全文を自力で写せること」「言葉の意味を理解すること」が大切だと思っています。
むしろ、字を間違えたときは、「正しい形を覚えよう」という前向きな姿勢になれる良い機会。写経は、文字に丁寧に向き合う中で、自分の思考や記憶のクセにも気づかせてくれる作業なのかもしれません。
ノート1ページ分書くと、ちょっとした達成感と爽快感がある
般若心経は262文字。ノートに1ページ分くらいの分量です。無理なく1日で書き終えられる長さということもあり、1回写し終えると「ちゃんと最後まで書いた」という小さな達成感があります。
しかも、不思議と書き終えたあとは、頭が少しスッキリしています。無心とまではいかないけれど、「あれこれ考えすぎていたな」とか、「目の前のことに集中するって、やっぱり気持ちいいな」と感じられる時間になっています。
これが、写経のもたらす“心の整え方”なのかもしれないと、実感するようになりました。
無心にはなれなくても、集中はできる
写経=無心というイメージがありますが、実際にやってみると、完全な無心になるのは簡単ではありません。書いている途中で、「さっきの字、曲がってたな」とか、「この漢字の意味なんだっけ?」といった雑念が出てきます。
でも、それでもいいのだと思います。大事なのは、途中で立ち止まらずに、そのまま一文字一文字を丁寧に写していくこと。と言っても私はけっこう雑に書いていますが。ただし、字が間違っていないかは注意しています。雑念に気づいて、それでも手を止めずに書き続ける。その繰り返しが、自然と集中につながっていきました。
写経は“無になる訓練”というよりも、“いまここにいる自分を見つめる時間”なのかもしれません。シャーペン1本でも、それを十分に感じられたことが、私にとっての大きな発見でした。
初心者におすすめの写経の目標と取り組み方
「全文を自力で書く」「意味を理解する」ことを目標に
私が写経を始めたときに立てた目標は、「全文を自力で写せるようになること」と「言葉の意味を理解すること」の2つでした。
きれいな字で書くとか、仏教の深い教えを完全に理解するといったことは、今の自分にとってはハードルが高すぎます。でも、「般若心経の262文字を自分の手で一文字ずつ書いてみる」「この言葉はどういう意味だろうと少し調べてみる」といった、小さな目標なら気軽に取り組めます。
写経は、どんなに忙しくても1日5分〜10分あればできます。1日数行でも構わないので、まずは「続けること」を意識して取り組んでいます。
最初は「字のきれいさ」は気にしなくていい
本来、写経は丁寧に書くことで集中でき、さらには無心になれるのだと思います。しかし、今の私の段階では、とにかく書いてみることが一番大事だと感じています。
「きれいに書こう」と力が入りすぎると、逆に手が止まってしまいます。最初は「自分なりに丁寧に」くらいの感覚で十分だと思います。
1日1段落でもOK|自分に合ったペースで
毎日全部を書き写そうとすると、途中で疲れてしまったり、忙しくてできない日が出てくるかもしれません。だから私は、「1日1段落」「5分だけ」といった柔らかいルールを自分に課すようにしています。
般若心経は、リズムよく句読されているので、1つの句ごとに区切って取り組むのにも向いています。たとえば「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時〜」の1行だけでもいい。それでも確実に前進している感覚があるので、モチベーションも維持できます。
何より大切なのは、無理をしないこと。続けられる形を見つけることが、写経を日常に取り入れる最大のコツだと思います。
鉛筆・シャーペン写経におすすめの道具と準備
自分に合った濃さの鉛筆やシャーペンを選ぼう|HBやクッション付きもおすすめ
写経をシャーペンや鉛筆で行う場合、特別な道具をそろえる必要はありませんが、自分にとって書きやすいものを選ぶと、集中しやすくなります。
たとえば私は、HBの0.9mm芯を使っています。2Bに比べると筆跡はやや薄いですが、そのぶんさらさらと軽やかに書けて疲れにくく感じています。以前2Bを使ったときは、芯がすぐに崩れたり、細かい粉が出たりして、気になってしまいました。
とはいえ、これもあくまで私の感覚です。人によっては「濃い字の方が集中できる」「柔らかい芯のほうが気持ちいい」という方もいると思います。結局のところ、写経は自分と向き合う作業ですから、普段使い慣れている筆記具の濃さで始めるのが一番自然だと思います。
筆ペンのような風合いにはなりませんが、慣れた筆記具だからこそ「書くこと」に集中できるという安心感があります。形式にとらわれず、自分にとってストレスの少ない道具を選ぶのが、写経を続けるためのコツではないでしょうか。
ノートでもコピー用紙でもOK|ガイド線付きの写経用紙も◎
写経用の紙といっても、特別なものを用意しなくても大丈夫です。私はノートに、般若心経のテキストを見ながら書き始めました。
100円ショップなどでも写経用の練習帳が販売されていることがありますし、文具店ではきちんとした用紙も手に入ります。でも、最初は手持ちの紙で十分です。“始めやすさ”を優先した方が続けやすいと実感しています。
本やスマホで般若心経の読みや意味を調べながらでもOK
写経しながら「この言葉、どういう意味なんだろう?」と思ったときには、スマホでさっと検索しています。もちろん、集中力を途切れさせないように工夫は必要ですが、写経を通じて言葉の意味に興味を持つきっかけにもなります。
特に般若心経は、仏教の核心を短い言葉でまとめているため、一語一語の意味がとても深いです。全部を理解するのは難しいかもしれませんが、1つでも「なるほど」と思える言葉に出会えると、写経の時間がより豊かなものになります。
まとめ|写経は「完璧にやること」より「続けること」が大切
写経というと、筆や墨、静かな部屋、整った姿勢…と、きちんとした準備が必要なものだというイメージがあるかもしれません。もちろん、そうした環境で心を整えながら書く写経も素晴らしいものだと思います。
でも、私のように「今の自分にできる範囲で始めたい」という人にとっては、筆にこだわらず、シャーペンや鉛筆で手軽に始めることこそが、一歩を踏み出す大切なきっかけになります。
字が上手じゃなくてもかまいません。途中で間違えても、また書き直せばいい。意味がすぐに理解できなくても、少しずつ調べていけばいい。完璧じゃなくても、「自分で書いて、自分で気づいていく」ことに意味があると、写経を通して実感しています。
何より、ほんの数分でも机に向かい、1行でも文字を書いていると、頭や心が少しスッキリする。そんな小さな変化や気づきの積み重ねが、日常の中の“静かな時間”を生んでくれるように思います。
写経は、特別な人のための修行ではありません。道具や形にとらわれず、今の自分が無理なく続けられる方法を見つけていくこと。それこそが、心を整える本当の写経ではないかと感じています。